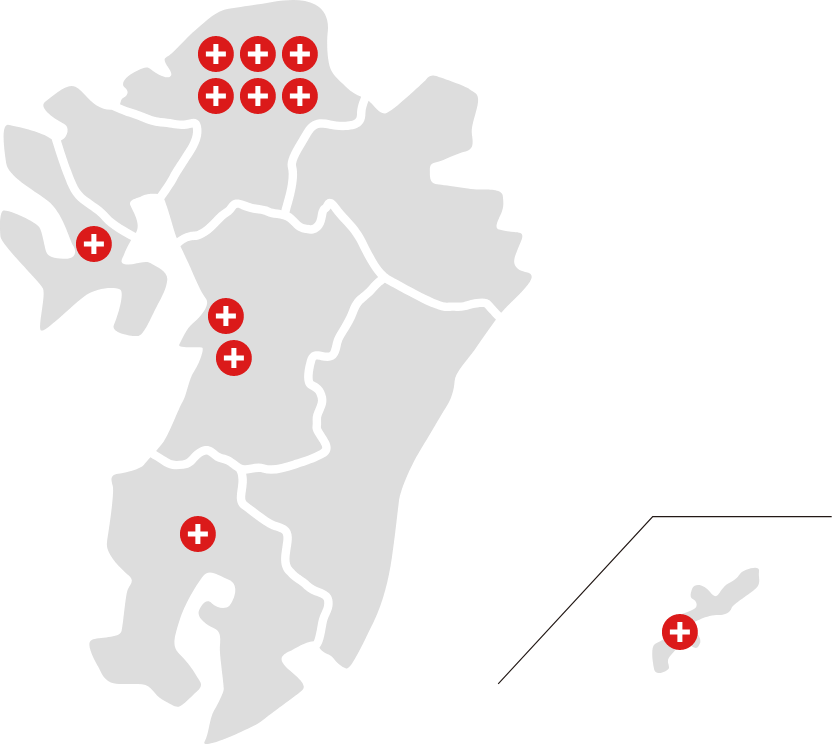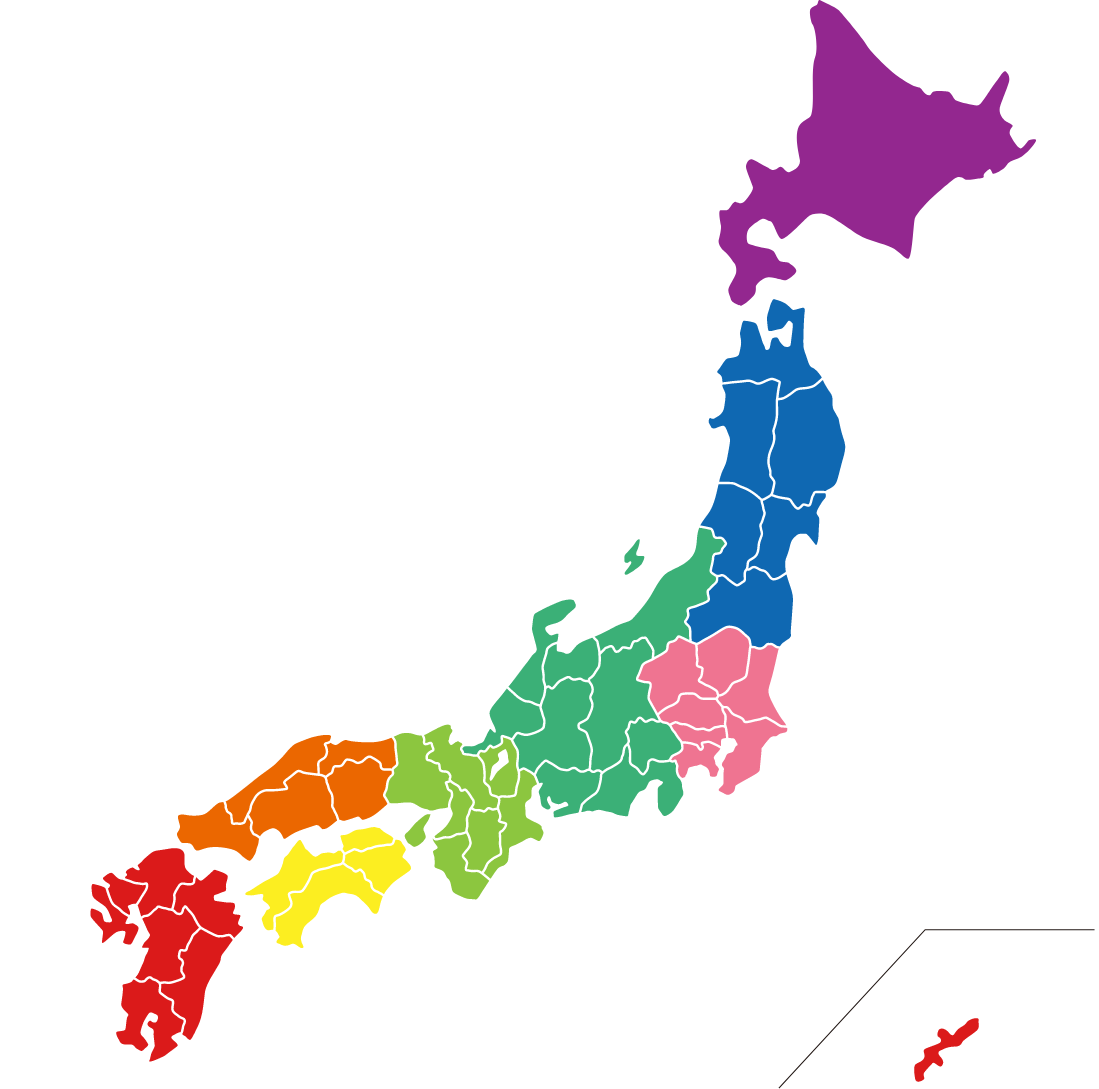Current JIPS REGISTRY Status
Current Number of Cases
867cases
Case registration ended on February 26, 2018
The Number of Facilities
85facilities
Update date: 4/16/2019
Reports in Japanese
We have been reporting on conference presentations and meetings in Japanese.
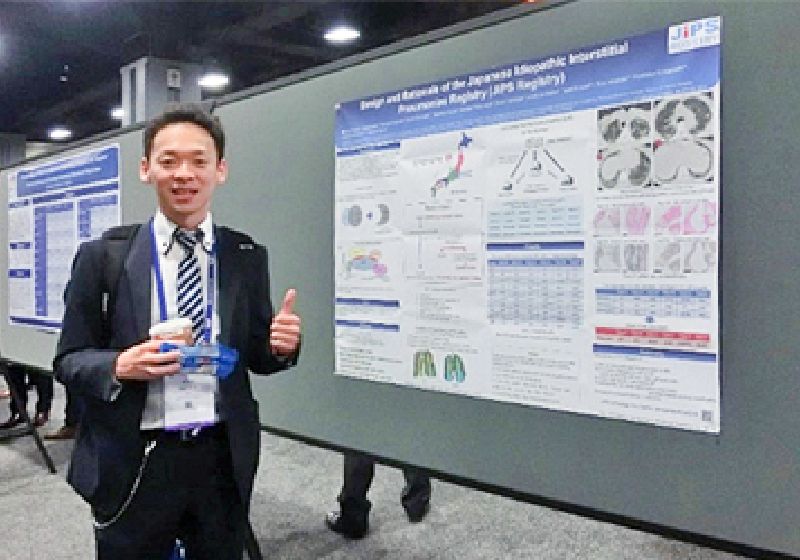
Hokkaido
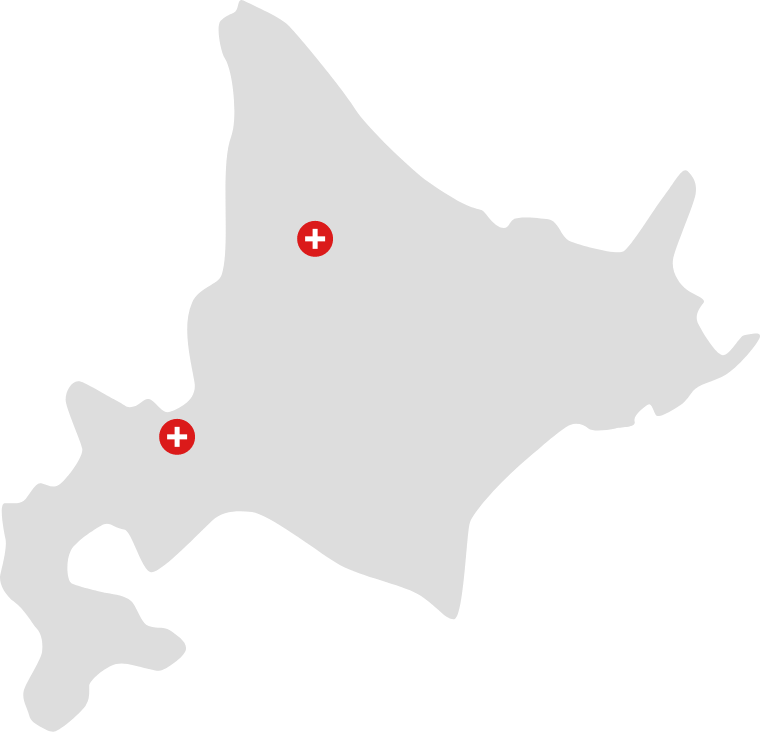
Tohoku
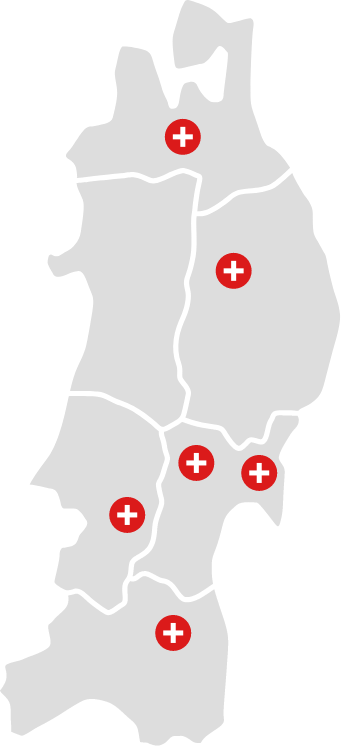
Chubu
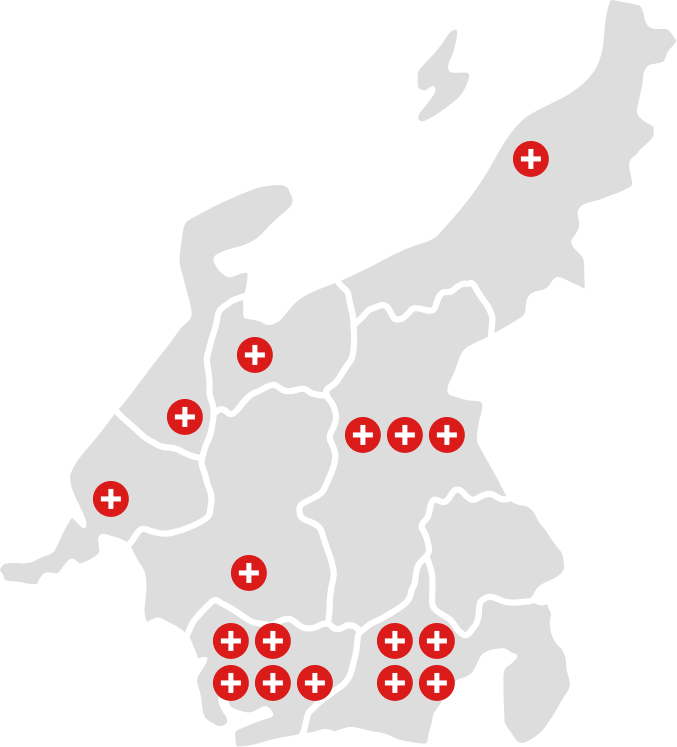
Kanto
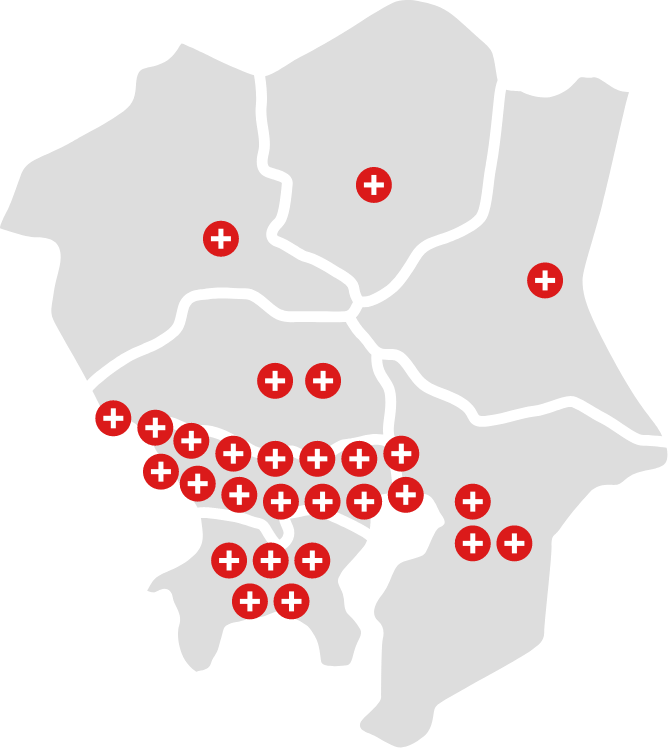
Kinki
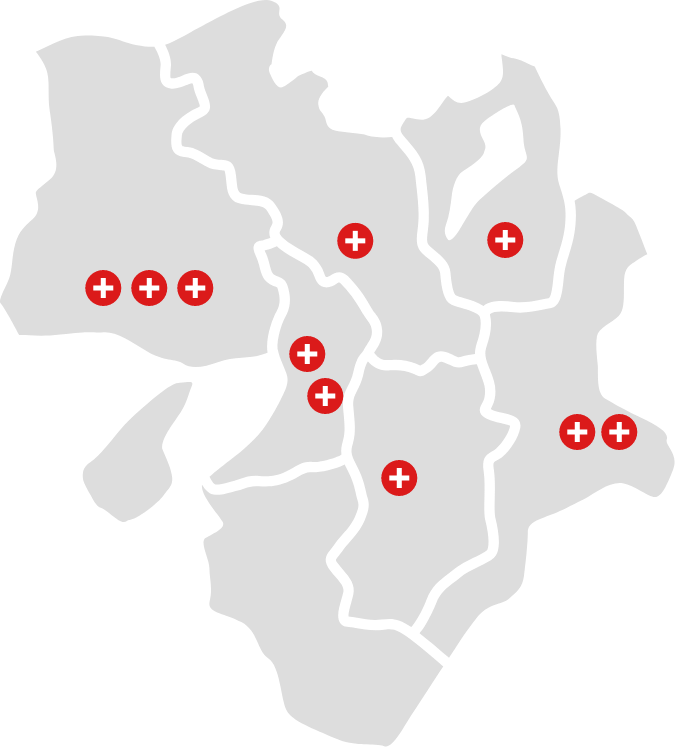
Chugoku
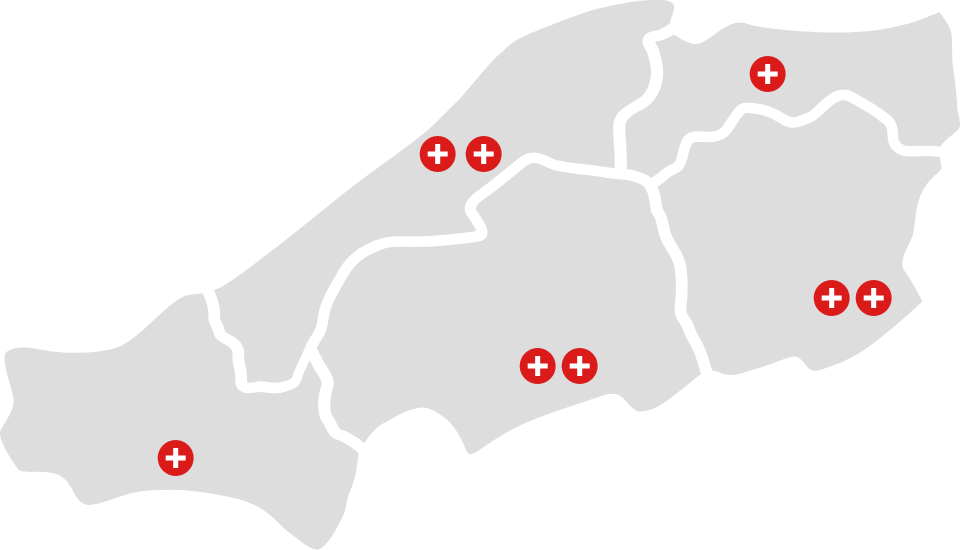
Shikoku
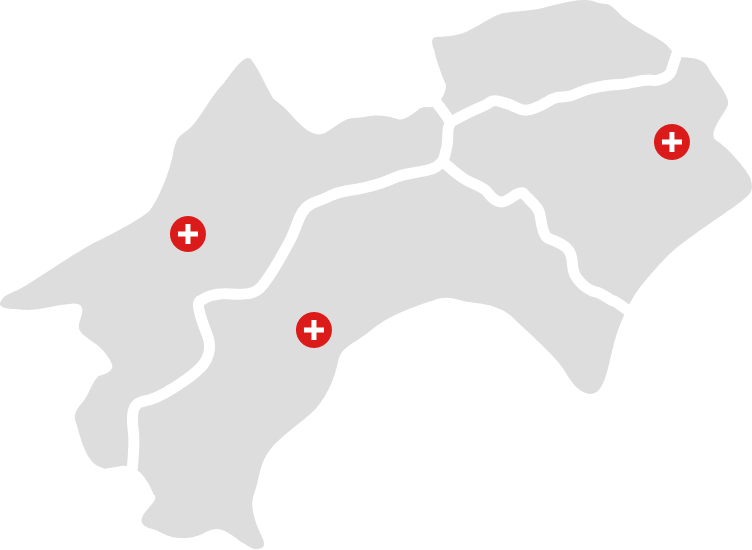
Kyushu